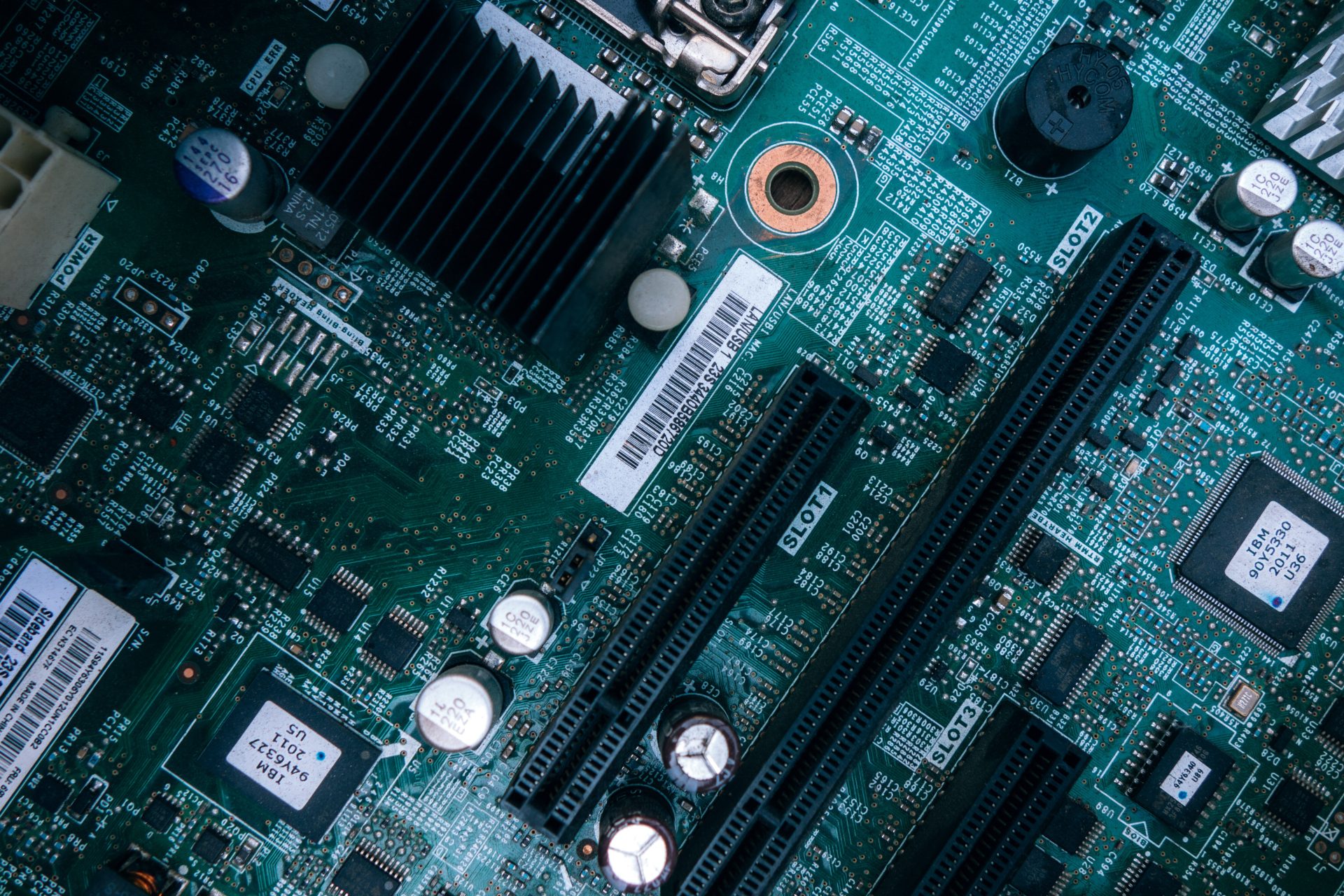Other parts of this series:
- 真の「生産性向上」と業務プロセス再構築、そして人の重要性海外先進事例に学ぶデジタル変革実現の鍵とは? ~ウェビナー
- RPAの要諦と次なるデジタル変革への挑戦 ~ウェビナー
- 「アンバンドル」から「社会構造変革」へ:日本におけるフィンテックの将来的可能性 ~ウェビナー
- 来たる“創造的破壊”の波に向けた、保険ビジネスのあり方とは ~ウェビナー
- デジタルウェルスマネジメントがもたらすアドバイスモデルの転換 _真の顧客本位の実現に向けて ~ウェビナー
- コーポレート領域でのデジタル技術導入による変革効果の限界と打開策–RegTechを中心とした効果創出の仕組みづくり ~ウェビナー
- HUMAN + MACHINE:ビジネス変革における第3の波に日本企業はどう立ち向かうべきか ~ウェビナー
- ブロックチェーンは金融ビジネスをどう変えるか、何が可能になるのか~ウェビナー
- デジタル変革のあるべき姿 – 伊予銀行様DHDバンクを例に ~ウェビナー
- デジタル変革の鍵を握るCloud活用をどう進めるべきか – 金融業界における成功の要因 ~ウェビナー
- 真の顧客起点型ビジネスモデルの追求 –2つの主導権争いと鍵となるテクノロジーの展望~ウェビナー
- デジタルトランスフォーメーション(DX)における人材活用・リスキルの進め方とは~ウェビナー
- 顧客を知り、顧客に応え、顧客と共に育てるビジネス ー 2019年消費者動向調査を踏まえて ~ウェビナー
- Beyond RPA -RPAは期待した効果を出せたのか?これまでの総括と求められる次なる一手:第1回 RPAの特性と活用推進の鍵 ~ウェビナー
- BEYOND RPA -RPAは期待した効果を出せたのか?これまでの総括と求められる次なる一手:第2回 求められる次の一手と2つの方向性
- 第1回 グローバルのイノベーションにみる保険の新たな姿 _今だからできるサービスと日本への示唆~ウェビナー
- 第2回 グローバルのイノベーションにみる保険の新たな姿 _今だからできるサービスと日本への示唆~ウェビナー
- Bank4.0時代に向けた銀行変革 - “破”銀行、“創”銀行:第1回 Bank4.0時代の到来と国内金融機関への影響~ウェビナー
- Bank4.0時代に向けた銀行変革 - “破”銀行、“創”銀行:第2回 Bank4.0時代の“銀行”と実現に向けた鍵~ウェビナー
- 顧客価値と企業経営_Design Pivot 新しいデザインとの向き合い方 第1回 金融機関に求められる新たなビジネスデザイン~ウェビナー
- 顧客価値と企業経営_Design Pivot 新しいデザインとの向き合い方 第2回 新たなデザインとの向き合い方
- デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第1回ディスラプションの進行と金融業界の現状~ウェビナー
- デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第2回 変革へのロードマップ(1)オペレーティングモデル・シフト~ウェビナー
- デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第3回 変革のロードマップ(2)リソース・シフトとワーク・シフト
- 守るテストと攻めるテスト:第1回 創造的破壊(disruption)の進行と金融業界の現状
- 守るテストと攻めるテスト:第2回 創造的破壊(disruption)の進行と金融業界の現状~“攻めるテスト”の要諦
- BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のその先へ _これまでとデジタル化時代における 今後のあるべき姿 :第1回 新たな市場環境とアウトソーシングのかたち
- BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のその先へ - これまでとデジタル化時代における 今後のあるべき姿 第2回 ― BPSのメリットと活用事例
- COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト:第1回 COVID-19のインパクトと『ニューノーマル』のかたち
- COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト:第2回 先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト 銀行業界
- COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト 第3回 先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト〜証券・保険業界
- 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第1回 異業種連携の最新動向と金融サービスのポテンシャル
- 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第2回 異業種による金融参入事例〜MarCoPayの実現に向けた日本郵船の取り組み
- 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第3回 異業種による金融参入・連携における成功実現の要諦
- 保険イノベーションの最新動向 〜EFMA受賞イノベーションから見た次なる一歩とは:第1回 EFMAアワード受賞企業と保険イノベーションのトレンド
- 保険イノベーションの最新動向 〜EFMA受賞イノベーションから見た次なる一歩とは:第2回 保険会社が取るべき次なる一歩
- 筋肉質な経営体質に転換するための、聖域なきコスト削減 – リバウンドしない仕組みづくりとカルチャー変革
- 欧州デジタルバンキング、何が成否を分けたのか。そこから学ぶ日本への示唆とは:第1回
- 欧州デジタルバンキング、何が成否を分けたのか。そこから学ぶ日本への示唆とは:第2回
- 顧客体験を軸にしたビジネス変革 ~他業界に学ぶ顧客体験の追求と成長へのチャレンジ~
- 2021年の金融業界の展望 – 「ニューノーマル」を実現するために金融機関には何が求められるのか
- 「2025年の崖」を乗り越えるモダナイゼーションの現実的な施策とは その4 ~アクセンチュアの謎、なぜレガシーモダナイゼーションで選ばれるのか?
- データドリブン保険経営の要諦〜大同生命におけるビジネス・アナリティクス・クリエイティブ三位一体改革〜
- Capital Markets 2025 – 証券ビジネスの再創造に向けて
- Technology Vision 2021から読み解く日本の金融機関への示唆
- 日本初のデジタルバンク「みんなの銀行」は何を目指しているのか - 横田頭取・永吉副頭取をお迎えして
- 保険イノベーションの最新潮流~ Efma受賞イノベーションから見た最新事例と保険DXの将来像~
- 「パーパス起点」で金融機関はどう変わるのか ~ “Business of Experience(BX)”実現に向けた具体的な変革ポイント
- アウトソーシングの新潮流と人材戦略について
- 「事故のない世界」を目指して。イーデザイン損保の新たな自動車保険「&e アンディー」からパーパス起点の変革の意義を紐解く
- 2022年、金融機関の持続的成長には何が必要なのか。銀行・証券・保険の各業界のトレンドと展望を総括
- 銀行業界を牽引するグローバル大手銀行の戦略から、日本の金融機関への示唆を読み解く
- 岐路に立つ金融機関系システムは、10年後を見据えてどのように変わるべきなのか
- 金融機関のグローバル展開パターンを分析し、成功の要諦とシナジーの生み方を読み解く
- COVID19とは何だったのか。これまでの総括とこれからの予測、そして日本の金融機関への示唆
- メタバースは現実世界やビジネスをどう変えるのか。テクノロジー・ビジョン2022に寄せて
- 顧客ニーズの変化や手数料率の低下。証券リテール業界はどのように変わるべきなのか
- 保険イノベーションのグローバルトレンドと、今後起こりうる大きな変化。Qorus(旧Efma)受賞イノベーションから最新事例のご紹介
- 多様化するリスクに対し、日本の金融機関が取るべきデータドリブンなリスクマネジメントとは
- 顧客を「生活者」として捉え直す。真の顧客志向による顧客体験の最適化とマーケティングの変革
- 2023年の金融業界を占う。不確実な世界で持続的な成長と新たな価値創造を実現するための注力テーマ
- AI活用は意思決定の領域にまで拡大。金融業界におけるAI活用と「責任あるAI」の実現に向けて
- 金融機関におけるTalent Transformation(TX)の進め方
- イノベーションの潮流に変化の兆し。新興国のイノベーション事例から日本の金融機関は何を学べるのか?
- 社会実装が始まる量子コンピュータ。金融業界こそ量子コンピューティングを活用すべき理由とは
- ジェネレーティブAIが金融業界にもたらす巨大なインパクト。「AI社員」の活用事例も紹介
- コア領域こそ内製化を。DX全盛の今こそ金融業界のIT現場を取り巻く状況を知る
- アトム(現実)とビット(仮想)の融合が始まった。テクノロジービジョン2023から世界の向かう先を知る
- Qorus Innovation in Insurance Awards 2023の受賞イノベーションを解説。保険イノベーションの今後を占う
- “価値”そのものに着目した新たな変化の波。Web3の進化が金融業界にもたらす可能性について
- 【新年特別企画】銀行、証券、保険の各業界で生成AIの活用が本格化へ。2024年の金融業界を占う
- 生成AIが可能にする一人ひとりの顧客との対話。金融業界の多くの課題を解決しうる超高速マーケティングとは
- 保険契約管理業務をゼロベースで再構築。アフラック生命保険株式会社が全社横断で取組む「アフラック プロジェクトZERO」とは
- クラウド型統合融資プラットフォームnCinoが世界中で受け入れられている理由とは。融資事業のデジタル変革の道筋を考える
- Qorus Innovation in Insurance Awards 2024レポート。保険イノベーションの現在地と今後の展望を考察
- 業務変革を実現し、経営の“バディ”に。金融業界における生成AI活用の現在地と今後
- 【新年特別企画】生成AIを活用した変革が本格化へ。2025年の銀行・証券・保険業界の注力テーマを解説
- 新時代に突入したサイバーセキュリティ。経営アジェンダとしてのサイバーセキュリティ対策と将来態勢
- デジタルとAIが顧客の声を「戦略」に変える。マルチエージェントAIが導く金融マーケティングの未来
- リライトで勘定系を刷新。長野県信用組合様が挑む「ビジネス×システム×人材」三位一体のモダナイゼーション
- トークン化ビジネスの世界的潮流を紐解く。トークン化預金とステーブルコインが切り拓く決済の未来
第6回 金融ウェビナー
収益力の低下、規制強化、内部コストの増加、デジタル・イノベーションの加速やディスラプターによる既存ビジネスモデルへの挑戦など、日本の金融機関は数多くの課題に直面しています。こうした背景の下、コーポレート部門(財務・会計・リスク管理・コンプライアンス部門など)は、ビジネスのけん引役としてより積極的な役割を果たすことを求められており、RegTechの持つポテンシャルが大きな注目を集めています。
多くの金融機関は、コーポレート部門の効率化に向けた取り組みをすでに始めているでしょう。しかし、達成すべき目標はコスト削減だけではありません。コストセンターという既存の概念を超えて、業務改革や戦略推進、顧客体験の向上を支援し、社内外のステークホルダーに価値をもたらすことが求められているのです。
RegTechがもたらす変革
日本の金融機関にとって、こうした考え方は決して新しいものではありません。しかしRegTech、つまりコーポレート部門が活用するデジタル・テクノロジーが飛躍的に能力を高めつつある今、ゲームチェンジャーとしてさらに大きな役割が期待できるようになっています。
RegTechのポテンシャルが拡大する背景には3つの要因があります:
-
- データの質・量が急速に増大し、戦略的ツールとしての有効性が高まっていること
- ソフトウェア・テクノロジーの進歩により、プログラム言語に精通する専門家以外でも先進ツール(機械学習モデル構築など)の効果的活用が可能になっていることや、ディープラーニングなどソフトウェアそのものが進化している事
- クラウドコンピューティングがデータ管理の枠組みを超えて業務ノウハウの蓄積に活用されるなど、共創・共用が金融業界で広まっていること
ではRegTechはどのように活用され、コーポレート部門の変革にどのような役割を果たしているのでしょうか?ビッグデータ分析やAI、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンといったテクノロジーは、様々なかたちで利用されていますが、中でもアンチマネーローンダリング(AML)や顧客確認(KYC = Know Your Customer)の分野では活用が最も進んでいます。
その具体的事例の1つとして挙げられるのが、英国Ripjar社のケースです。同社は、自然言語処理(NLP)などのAI技術を活用し、個人や企業の金融犯罪リスクの計量化・サービスを提供する企業です。リスクベースで顧客管理(カスタマーデューディリジェンス)を支援する同社のAML・KYCサービスでは、AIを使って約300のニュースなどの外部情報源を解析し、金融犯罪に関連するキーワードを検知した場合にアラートを生成。コンプライアンス部門の業務時間短縮だけでなく、リスク兆候(レッド・フラグ)の見逃しによるネガティブ報道のリスク抑止にも役立てられる可能性を秘めています。このサービスの特徴として、重要な公的地位にある顧客のみならず、外部情報源に登場したすべての個人を対象としていることが挙げられます。
もう一つの事例は、住宅ローンの事前審査業務への活用です。アクセンチュアは信用リスク管理部門による社内審査基準(例えば貸倒率や延滞率など)を過去の審査履歴との相関から見直し、本人確認の読取や融資判断をAIに代替させる仕組みを開発しました。これまでは約2日かかっていた住宅ローン申請の回答期間をリアルタイムに短縮し、事前審査の申請件数も8倍に増加。このケースでは、RegTecの活用がバックオフィス業務の効率化だけでなく、顧客体験の向上とビジネス拡大にもつながっています。
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved.
“ゼロベース”の重要性
前述の通り、多くの金融機関はすでにAIをはじめとするRegTechの活用を進めており、コスト削減に成功するケースも見られます。しかし、コーポレート部門による価値創出という意味では必ずしも目立った成果を挙げられていないのが現状です。
その理由はどこにあるのでしょうか?日本の金融機関による取り組みには、共通して見られる2つの課題があります。
その1つは、多くのケースでデジタル変革の取り組みが部門内に“閉じた”かたちで行われているため、効果が限定的となっていることです。2つめは、取り組みが既存業務体制の枠組みの中で実施され、現場が直面する課題の分析からスタートする、つまり特定課題への対処療法としてデジタルツールが利用されていることです。
ウェビナーで解説したように、アクセンチュアはこうした課題へ対応するため2つの新たなアプローチを提案しています。その1つは、デジタル変革の推進を最優先項目として掲げ、既存業務の見直しに “ゼロベース”で取り組むことです。もう1つは、現場の業務ノウハウへ過度に依存せず、分析専門家の能力を活用してデータ重視(data driven)のアプローチを取ることです。これにより、蓄積されたデータを業務改革に不可欠な視点・レポーティングツールとして活用できるでしょう。上で紹介した住宅ローン業務の事例では、両方のアプローチが実際に取り入れられています。
RegTechの持つ真の価値は、コーポレート部門変革の推進役としてのポテンシャルにあります。革新的なレポーティングや経営指標、業務課題の特定アプローチなど、新たな経営管理手法を開発・実行するビジネス・アドバイザーへとコーポレート部門を転換させる力を秘めているのです。しかしテクノロジーを導入するだけで、こうした変革は実現できません。そのポテンシャルを余すところなく活用するため、日本の金融機関にはイノベーティブな思考がますます求められているのです。